|
|
 |
|
|
| 資料No.1[屋根の色とベンチレーターの色。] |
|
鉄道模型では屋根およびその周辺を見る機会が多いのに反し実物のそれらを正確に把握する事がなかなか難しいものです。模型が完成した後に同胞に「ココ違っているヨ!」と言われると情けないものです。 この資料No.1ではどうしたら実物に近づけるかを「屋根とベンチレータの色」に絞って記したいと思います。 もし,異なる見解がお有りの場合はメールにて教えて頂ければ幸いです。
まずお断りしなくてはならない事があります。 以下は「国電(ないしは省電)」に限っています。 また,大まかに整理しているため正確さに欠ける箇所もあります。 ・・・と言うといい加減とも思われがちですが「色の記憶はあいまい」であり「マンセル記号は近似値」と言う点で正確を期すことが難しいのです。 これらの点をご理解願います。
色を特定する根拠でもっとも有効な(信用に足る)資料は国鉄・車両設計事務所編集の「国鉄車両関係色見本帳(見本帳と記します)」です。この色見本帳は「昭和31年(西暦1956年」から始まり,以後数年おきに改訂がなされております。 ここで重要なのは「1956年版」に続く「1959年版」です。前者に於いて電車の屋根および通風器(ベンチレーター)は「淡緑2号」と指定されています。 しかし後者に成るとこれが「ねずみ色1号」に変わっています。 以降は「屋根およびベンチレーター,踏板,避雷器などねずみ色1号で指定」され判断に迷う事が無くなります。
これでどういう風に塗られていたかおおよそは検討が付くと思われます。また,「屋根布」ですがこれは布表面に金剛砂のような砂が付いたもので,わかりやすく言えば“サンド・ペーパー(布ヤスリ)”に酷似しています。 模型では「ルーフィングサンド」や「スウェード調スプレー」などで表現出来ます。以降,サンドペーパーのような屋根布を単に“屋根布”と記します。
さて,場合を「第2次世界大戦前(戦前と記します)」と「第2次世界大戦後(戦後と記します)」に分けます。
★「戦前」
ここでの対象車輛はモハ40形電車が登場した時期から昭和16年(西暦1941年)位までの間に存在していた車輛です。 この頃はまだカラー写真が少なく,残されたカラーも退色,変色している事を加味しなければ成りません。
また,屋根は反射などの影響で白く写る場合がある事も加味する必要があります。
色の特定には色見本帳がないので諸先輩の証言によるところが多いのが現状です。
急電・流電における色は実物を知る方々の証言により決めています,従って別の判断をされている方もいらっしゃると思います。 特にダブルルーフ車に関してはご存知の方があればお教え頂ければ幸いです。
★「戦後」
戦後すなわち昭和20年(1945年)から数年間は荒廃のさなかで断言出来る資料,証言がないのが残念です。 少なくとも上空から目立たないよう配慮されと思われます[補足2参照]。 昭和25年(1950年)3月から湘南電車[80形]の運転が始められ,目撃した人からベンチレーターの色についの証言が得られます(資料4参照)。 この頃から昭和33年頃まで,鋼板屋根車の屋根およびベンチレーター,踏み板ほかは淡緑2号に塗られていました。戦前に登場した鋼板屋根車はこの時期,屋根色が更に淡緑2号へ塗り替えられた可能性があります。
ところが昭和26年(1951年)に起きた桜木町事件後, 屋根の絶縁を強化する目的で鋼板屋根車の屋根は随時「イボ付きのビニールシート」を張る事と成りました。その結果, この処置を受けると屋根だけはイボ付きビニールシートの色と成りました。このため昭和26年から昭和33年頃までにいつこのシートを張ったのかによって屋根の色が異なる事に成り,この事が混乱を招ねく原因と成っています。
当工房 では一応,下記の表の通り決めていますが,実車の写真を見るなりして確認してから塗るよう心がけています。
昭和34年(1959年)以降,電車は屋根およびベンチレーターと共に「ねずみ色1号」に指定されているので混乱はありません。但し,木製屋根車に張った屋根布はなお残る事に成ります。
当工房ではこのイボ付きのビニールシートを張った屋根はすべて「ねずみ色1号」で塗っています。
屋根布のうちイボ付きのビニールシートの屋根布を“絶縁屋根布”と記します。
★補足
1. 屋根布はサンドペーパーのようなも のと記しましたが外見は金剛砂のようにキラキラ光っていたと証言(資料No.3参照)されていますが地色としては黒茶系統の色だったようです。 私の実感では,茶色に見える事が多く,撮影した写真を良く見ると砂がところどころ剥がれているように見えます。 また,或る写真によると白く見える(反射とは思えない)屋根がありますが白地系統の屋根布もあったのか,屋根布をベンチレーターと共に同色に塗ってしまったのか?・・・興味のある事です。また,パンタグラフ周辺は集電子(シュー)から出る銅粉で特に茶色に見えたそうです。一方,多くの場合,ベンチレーターの色が淡緑2号なら「踏み板,避雷器,ヘッドライト(例外あり:黒)」も同色(淡緑2号)に成っていました。
2.戦中に登場(剛体改造車含む)した戦時設計の車輛は物資の都合で木製屋根,すなわち屋根布タイプでした。 飯田線で最後を迎えたクモハユニ64000は屋根布を張られていました。
3. イボ付きビニールシートは本来の「絶縁性強化」のほか「防水」も兼ねて昭和26年頃から鋼板屋根車に張られましたが検査工場(線区)によっては戦前戦中の木製屋根車にも適用した例(飯田線,身延線,仙石線など)があります。
4.戦後・鋼板屋根車(イボ付きビニールシート)の一例:
・73系(新製車),「モハ72690以降の車輛」「モハ72850番代車」「クハ79421~439(奇数),444以降の車輛」
「全金及び全金試作車(920番台車)」。
・70系(新製車),「モハ70053以降の車輛」「モハ71(一部改造車を含む)」「クハ76064以降の車輛」「全金車(300番代車)」。
・80系(新製車),「全金車(300番代車)」。
尚「モハ80の200番代車及びクハ86,サハ87の100番代車」から“張り上屋根”でなくなり絶縁屋根布が全体に張られた。
★塗料ほかの入手
これらの塗料は「日光モデル」で入手出来ます(鉛丹色を除く)。 色見本帳を基に出来る限り正確な色を再現している製品で,既に廃色と成っている色も扱っています。 ルーフィングサンドは「エコーモデル」で扱っています。
以上を踏まえて当工房に於いては以下の通り色を塗っています。[塗装のみならず製作に当たっては,資料を出来るだけ集めて行うのが理想です。
とは言ってもこのようなこだわり持つ以前に完成した模型の中で誤りのある模型も有り,これらはいつか直すつもりです。] |
| ★戦前の国電(省電),その屋根とベンチレーターほかの色について |
| 区分 |
屋根色 |
ベンチレーター色 |
備 考 |
| ダブルルーフ車 |
鉛丹(えんたん)色 |
鉛丹色(片ガーラント) |
踏板も同色。 |
| 木製屋根車 |
ルーフィングサンド(屋根布) |
黒(ガーラント) |
踏板も同色。 |
| 鋼板屋根車 |
灰青(はいじょう)色 |
灰青色 |
踏板も同色。モハ41,51,60,50形の張り上げ車。 |
| 急電・流電 |
灰青色 |
灰青色 |
モハ52形ほか,踏み板,パンタグラフも同色。 |
| 急電・合の子 |
ねずみ色 |
ねずみ色 |
モハ43形ほか,踏み板,パンタグラフも同色。 |
| 急電の色は当時,実物を見た事のある先輩の証言を基としています。 流電以外の灰青は推定によります, 灰色系で異論はないと思います。 |
|
| ★戦後の国電,その屋根とベンチレーターほかの色について |
| 区分 |
屋根色 |
ベンチレーター色 |
備 考 |
| ダブルルーフ車(昭和20~33年) |
淡緑2号又はルーフィングサンド |
淡緑2号(片ガーラント) |
明り窓周辺部は淡緑2号。 |
| 木製屋根車 |
ルーフィングサンド(屋根布) |
淡緑2号 |
踏板,避雷器は淡緑2号。 |
| 鋼板屋根車(昭和24~33年) |
淡緑2号 |
淡緑2号 |
踏板,避雷器も同色。 |
| 鋼板屋根車(絶縁布張り)(昭和27~33年) |
ねずみ色1号 |
淡緑2号 |
避雷器は淡緑2号。 |
| 昭和34年以降 |
|
| 鋼板屋根車(絶縁屋根布張り) |
ねずみ色1号 |
パンタ踏板,避雷器も同色。 |
| 昭和32年(1957年)落成時の101形試作車のベンチレーター,避雷器は「淡緑2号」でした。[資料5参照] |
|
| 1983 国鉄車輛関係色見本帳 |
戦前のダブルルーフ車(鉛丹色) |
 |
.jpg) |
| 戦前の木製屋根車(屋根布張車) |
戦前の鋼板屋根車[塗色(推定):灰青],屋根は塗装しただけ。 |
.jpg) |
.jpg) |
| 急電・流電(戦前)[塗色(或る証言による):灰青色] |
急電・流電(戦後)[左車輛の飯田線時代] |
.jpg) |
.jpg) |
| 戦前,戦後鋼板屋根車(屋根は塗装,絶縁対策なし),淡緑2号 |
戦前,戦後鋼板屋根車(絶縁強化対策実施車) |
済みません,製作車がありません。
(一例)
鋼板屋根車,淡緑2号塗り(踏み板も同色)です。 |
済みません,製作車がありません。
(一例)
左車輛の屋根絶縁強化タイプ(絶縁屋根布張り)です。
屋根の色:ねずみ色1号
ベンチレーターの色:淡緑2号
踏み板は撤去されました。
この対策で張り上げ屋根が普通屋根化された車輛があります。 |
| 桜木町事件以降の鋼板屋根車(絶縁布張り車) |
昭和33年までに登場した「新性能電車」 |
.jpg) |
.jpg) |
| 昭和34年以降から,ベンチレーターの色は「ねずみ色1号」に変わる。 |
| 昭和34年以降まで残った木製屋根車(屋根布) |
昭和34年以降の戦後鋼板屋根車(絶縁布張り車) |
.jpg) |
.jpg) |
| 80系のうち通称100番代(モハ80は200代)の前に登場した車輛は張り上げ屋根(更新修繕を受けるまで)だったので注意。 また,70系のサロは80系サロの設計に準じていたため同様に張り上げ屋根でした。 すなわち,屋根の中央(頂上)周辺のみ木製屋根の構造でこの部分は屋根布を張っていました。更新修繕の後は絶縁屋根布を全体に張った車輛が多く見られるように成りました。 |
| サハ85001(木製屋根部と共に絶縁屋根布を全体に張った例。) |
サハ75106[3扉改造車],張上げ屋根の構造が分かる。 |
.jpg) |
.jpg) |
|
| 参考資料 |
| No |
資料名 |
通巻 |
記事(内容) |
著者,編者(敬称略) |
Page |
備考 |
| 1 |
1983 国鉄車輛関係色見本帳 |
- |
|
国鉄車輛設計事務所 |
|
|
| 2 |
国鉄電車回想Ⅱ |
- |
|
巴川享則 |
|
|
| 3 |
鉄道ピクトリアル |
721 |
鋼体化モハ50系と62系 |
|
43 |
|
| 4 |
METAL CAR |
3 |
僕のノート |
モハ40生 |
18 |
80系出場時の色。 |
| 5 |
レイル・マガジン |
252 |
最盛期の国鉄車輛 25 |
浅原信彦 |
111 |
写真: 三谷烈弌 氏。 |
| 6 |
鉄道史料[鉄道資料保存会刊] |
33~37 |
50系省電(Ⅰ)~(Ⅰ) |
奥野利夫 |
1 |
国電メモリアル |
|
 |
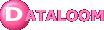 |
 |
 |
 |
 |
|
| 製作記 |
資料集 |
ギャラリー |
サイトマップ |
問合せ |
トップページ |
|